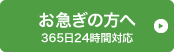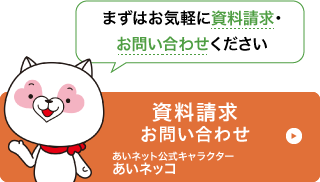2025.02.10(月)
- 葬儀
葬儀の持ち物ガイド|マナーや注意点も紹介
「急な訃報で、葬儀に何を持って行けばいいのかわからない…」「男性と女性で持ち物は違うの?」「親族として参列する場合、特別な準備は必要?」
そう思う方もいらっしゃるかもしれません。
葬儀の持ち物は、性別や立場、宗教・宗派によって異なります。マナーを守り、故人や遺族に失礼のないよう、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
この記事では、葬儀の持ち物について、必需品やあると便利なもの、服装マナーまで詳しく解説します。さらに、宗教・宗派別の注意点や、季節に応じた持ち物についても紹介しますので、急な訃報でも慌てずに準備ができるようになります。この記事を読めば、葬儀のマナーを理解し、心穏やかに故人を見送ることができるでしょう。
葬儀の持ち物|基本マナーと必需品
葬儀に参列する際は、故人や遺族への敬意を表し、適切な持ち物を準備することが大切です。ここでは、性別や立場を問わず、共通して必要となる基本的な持ち物と、そのマナーについて解説します。
香典:金額相場と表書きのマナー
香典は、故人への供養の気持ちを表すものであり、葬儀の際に遺族に渡す金銭のことです。香典の金額は、故人との関係性や自身の年齢、地域の慣習などによって異なります。一般的には、友人・知人の場合は5,000円~10,000円、特に親しかった場合は10,000円~30,000円、親族の場合は10,000円~100,000円が相場とされています。ただし、香典の額は故人や遺族との関係性、地域の慣習、自身の年齢や社会的地位によって変わるため、周囲の状況などを考慮して判断する必要があります。香典袋の表書きは、宗教・宗派によって異なりますので注意が必要です。
宗教・宗派別の香典袋の違い
仏式の場合、49日法要前は「御霊前」、49日法要後は「御仏前」が一般的です。浄土真宗の場合は、時期を問わず「御仏前」を用います。神式の場合は「御玉串料」や「御榊料」、キリスト教式の場合は「御花料」と書くのが一般的です。どの宗教・宗派か分からない場合は、「御霊前」と書いておけば問題ありません。香典袋は、文具店やスーパー、コンビニエンスストアなどで購入できます。
数珠:種類と正しい持ち方
数珠は、葬儀や法要の際に使用する仏具です。仏式では、数珠を持参するのがマナーとされています。数珠には様々な種類がありますが、大きく分けると宗派別の「本式数珠」と、宗派を問わず使える「略式数珠」があります。葬儀に参列する際は、略式数珠を持参すれば問題ありません。数珠は、歩く時など、合掌時以外は左手首にかけるか、左手で房を下にして持ちます。合掌の際は宗派によって持ち方が異なる場合があるので、事前に確認しておくとよいでしょう。数珠は、仏具店やオンラインショップで購入できます。
袱紗:選び方と包み方のマナー
袱紗は、香典袋を包むための布です。香典を裸のまま持ち運ぶのはマナー違反とされていますので、必ず袱紗に包んで持参しましょう。袱紗には様々な色がありますが、葬儀の際は、紫や紺、グレーなどの寒色系のものを選ぶのが一般的です。袱紗の包み方には、「略式」と「台付き」の2種類があります。略式の場合は、袱紗をひし形に広げ、中央よりやや右側に香典袋を置き、右、下、上、左の順に包みます。台付きの場合は、台の上に香典袋を置き、同様に包みます。袱紗は、百貨店や呉服店、オンラインショップで購入できます。
【男性編】葬儀の持ち物リストと服装マナー
男性が葬儀に参列する際は、女性とは異なる持ち物や服装マナーがあります。ここでは、男性の必需品や、服装に関する注意点について解説します。
必須の持ち物一覧
男性が葬儀に参列する際に必要な持ち物は、、数珠、、黒いネクタイ、黒い靴下、黒い革靴、黒いベルト、白もしくは黒のハンカチなどです。携帯電話は、マナーモードに設定するか、電源を切っておきましょう。
喪服・スーツのマナーと選び方
男性の喪服は、ブラックスーツが基本です。シングルとダブルのどちらでも問題ありませんが、ダブルの場合は、前ボタンを全て留めるのがマナーです。シャツは白無地のレギュラーカラーを選びましょう。ネクタイは、必ず黒無地のものを着用します。光沢のある素材や、派手な柄のものは避けましょう。
靴・ネクタイ・小物の注意点
靴は、黒の革靴で、金具などの装飾がないシンプルなデザインのものを選びます。エナメル素材やスエード素材のものは避けましょう。靴下も必ず黒無地のものを着用します。ベルトも黒でシンプルなデザインのものを選びます。時計は、華美なデザインのものは外し、シンプルなものを選びましょう。

【女性編】葬儀の持ち物リストと服装マナー
女性が葬儀に参列する際は、男性とは異なる持ち物や服装マナーがあります。ここでは、女性の必需品や、服装に関する注意点について解説します。
必須の持ち物一覧
女性が葬儀に参列する際に必要な持ち物は、数珠、黒いバッグ、黒いストッキング、黒いパンプス、黒いハンカチなどです。アクセサリーは、結婚指輪以外は外すのが基本です。ネックレスを着用する場合は、一連のパールネックレスを選びましょう。
喪服・ワンピース・バッグのマナー
女性の喪服は、黒のワンピースやアンサンブル、スーツなどが一般的です。肌の露出を控えることがマナーとされていますので、スカート丈は膝が隠れる長さのものを選びましょう。バッグは、光沢のない黒の布製のものを選びます。ハンドバッグやクラッチバッグが一般的です。
メイク・髪型・アクセサリーの注意点
葬儀の際のメイクは、ナチュラルメイクを心がけましょう。派手な色のアイシャドウや口紅は避け、落ち着いた色味のものを選びます。髪型は、清潔感のあるスタイルを心がけ、長い髪は後ろで一つにまとめます。ヘアアクセサリーを使用する場合は、黒や紺などの目立たない色のものを選びましょう。アクセサリーは、結婚指輪以外は外すのが基本です。ネックレスを着用する場合は、一連のパールネックレスを選びます。
ストッキング・靴のマナー
ストッキングは、必ず黒の無地のものを着用します。靴は、黒のパンプスで、ヒールの高さは3cm~5cm程度のものを選びます。光沢のある素材や、金具などの装飾があるものは避けましょう。
宗教・宗派別の葬儀の持ち物と注意点
葬儀の持ち物は、宗教・宗派によって異なる場合があります。ここでは、主要な宗教・宗派別に、持ち物の注意点について解説します。
仏式の場合
仏式の葬儀では、数珠を持参するのが一般的です。香典袋の表書きは「御霊前」としますが、浄土真宗の場合は「御仏前」とします。
神式の場合
神式の葬儀では、数珠は不要です。香典袋の表書きは「御玉串料」や「御榊料」とします。
キリスト教式の場合
キリスト教式の葬儀では、数珠は不要です。香典袋の表書きは「御花料」とします。
葬儀で「あると便利」な持ち物リスト
ここでは、葬儀に参列する際に、持っていると便利な持ち物について紹介します。
ハンカチ・ティッシュ
涙を拭いたり、汗を拭いたりするために、ハンカチやティッシュは必需品です。ハンカチは、白か黒の無地のものを選びましょう。
予備のストッキング・小物類
女性の場合、ストッキングが伝線してしまうことがありますので、予備のストッキングを持参すると安心です。また、ヘアピンや安全ピンなどの小物類も、いざという時に役立ちます。
季節別・状況別に配慮した葬儀の持ち物
葬儀に参列する際は、季節や状況に応じた持ち物を準備することも大切です。ここでは、季節別・状況別に、配慮すべき持ち物について解説します。
夏場の暑さ対策
夏場の葬儀では、暑さ対策が重要です。具体的には、扇子やうちわ、汗拭きシート、日傘などを持参するとよいでしょう。また、水分補給のために、ペットボトルのお茶や水などを持参するのもおすすめです。
冬場の防寒対策
冬場の葬儀では、防寒対策が重要です。具体的には、コートやマフラー、手袋、カイロなどを持参するとよいでしょう。足元の冷え対策として、厚手の靴下やブーツを着用するのもおすすめです。
雨天時の対応
雨天の葬儀では、雨具の準備が必要です。具体的には、傘やレインコート、タオルなどを持参するとよいでしょう。足元が濡れないように、防水加工の靴を履くのもおすすめです。
子ども連れの場合に必要なもの
子ども連れで葬儀に参列する場合は、子どものための持ち物も必要です。具体的には、おむつやおしりふき、着替え、飲み物、おもちゃなどを持参するとよいでしょう。子どもが飽きないように、絵本やぬいぐるみなどを持参するのもおすすめです。
宿泊を伴う場合の持ち物
遠方の葬儀に参列するなどで宿泊を伴う場合は、宿泊に必要な持ち物も準備しなければなりません。着替えや洗面用具、常備薬など、普段の旅行で必要なものに加えて、数珠や袱紗なども忘れずに持参しましょう。また、宿泊先の情報(ホテルの住所や電話番号など)を記したメモも、万が一に備えて持っておくと安心です。
以上が、葬儀の持ち物に関するガイドとなります。大切な方を亡くされた悲しみの中、慣れない準備に戸惑うこともあるかと思います。しかし、この記事で紹介した内容を参考に、マナーを守った持ち物や服装で参列することで、故人や遺族への敬意をしっかりと表すことができるでしょう。
平安祭典では葬儀に参列する際に知っておきたい基本的なマナーや注意点などを動画でもわかりやすく解説しております。ぜひご覧ください。